人材の獲得が、激しさを増しています。そうしたなかで、各社が取り組みを強めているのが採用ブランディングです。
厳しさを増す採用環境
本書によると、2024年の大卒有効求人倍率は1.71倍でしたが、従業員300人未満の企業に限定すると6.19倍にもなるそうです。つまり単純計算なら、5人採用するためには31人の学生を確保しなければなりません。中小企業にとって、新卒の確保はかなり難易度の高い課題といえます。
そうしたなかで、各社が取り組みを始めているのが採用ブランディングです。
180度ベクトルが変わった人事部の仕事
就職氷河期には常に求職者が過剰であり、企業は〇〇ナビなどの採用ポータルに掲載して、応募してきたなかから採用者すれば定員を充足できました。つまり学生を「選ぶ」ことが人事部の業務でした。いまはこれが180度変わり、自社をアピールしなければ応募そのものがなく、むしろ学生からいかにして「選ばれる」かが課題となっています。現代の人事部は、管理部門というよりも、マーケティングやブランディングの意識が求められています。その一つの表れが、採用ブランディングといえるでしょう。
人事部はマーケティングやブランドを担う部署に
本書のいう、採用広報のポイントはまさに営業活動です。ターゲットを見極め、彼らが重視することを知り、その中で「他社と差別化できない」ものは最低限業界水準を維持しつつ、「他社と差別できる」ことを作って積極的に広報施策を実施していきます。その際重要なのは、ターゲットを広げすぎず、企業文化に合った求める人材像を明確に思い描いて、そこにしっかり刺さる内容にすることです。特に採用広報の場合は、入社する数名~数十人にだけ響けばよいので、思い切りとがってもよいのでしょう。
一部に、極端に高い初任給を掲げる会社もありましたが、中小企業では初任給や年間休日数といった基本的な要素はほぼ各社横並びで、差別化できる要素ではなくなりました。また各種のアンケートを見ると、学生もむしろ企業理念や社風、やりがいを重視しているといいます。
人事部はより重要な部門に
こうした状況で、人事部は非常に強いプレッシャーにさらされる部門となっています。しかし、それは逆に人事部の価値を高めている側面もあります。本書によれば、理念共感を基本として、学生に選ばれる会社とは何かを考えて活動することは、企業理念の社内浸透を大いに促すと言います。つまり、人事部起点で組織全体の意識を変えることもできるのです。新卒採用は厳しいタスクですが、粘り強く取り組み、これを乗り越えることで組織の進化をもたらすこともできるのです。
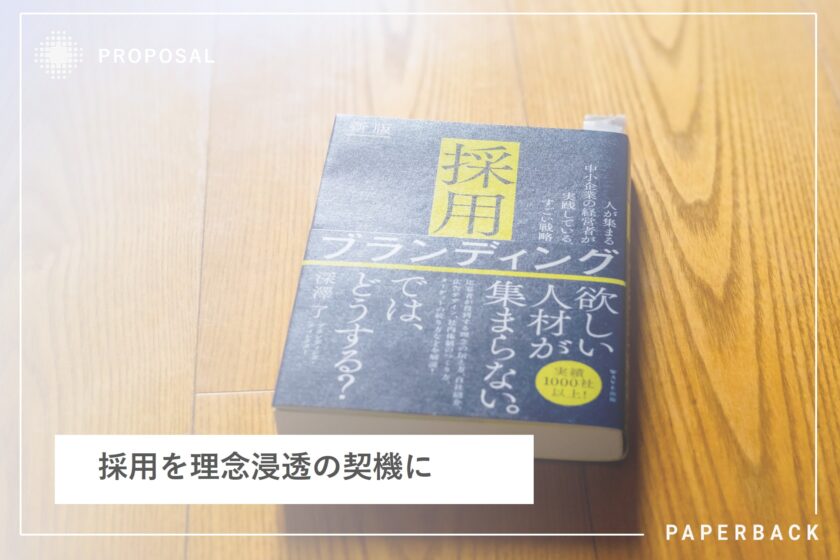
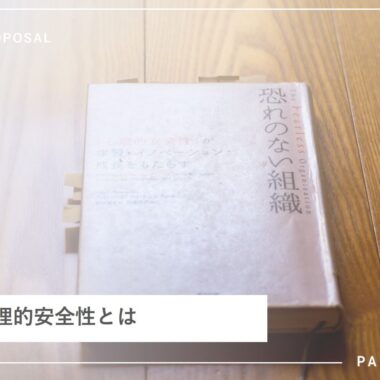
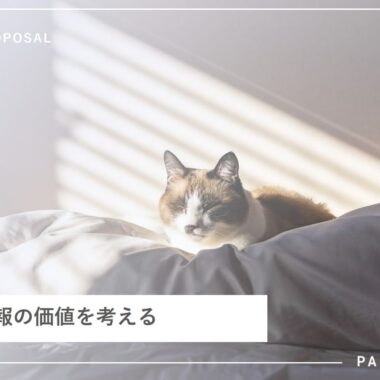
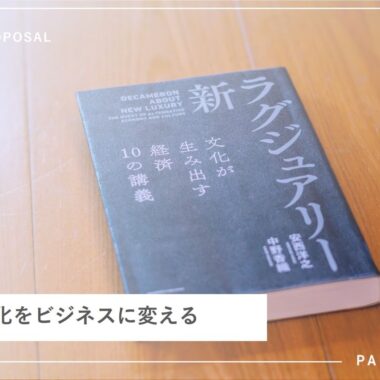

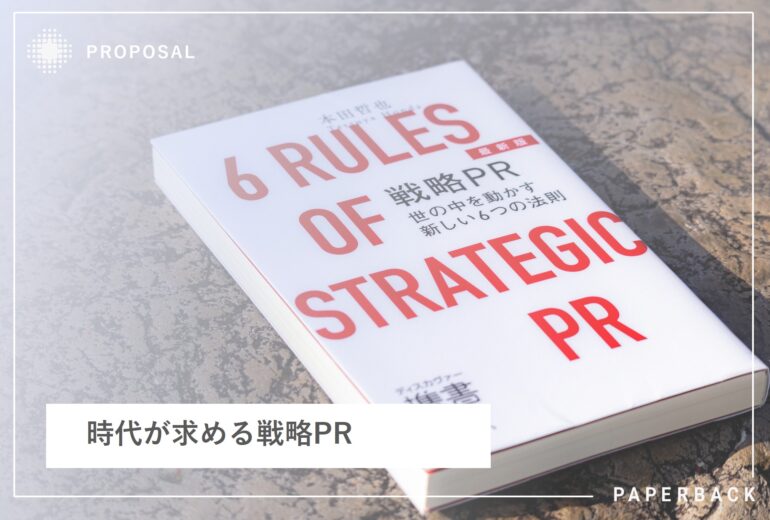
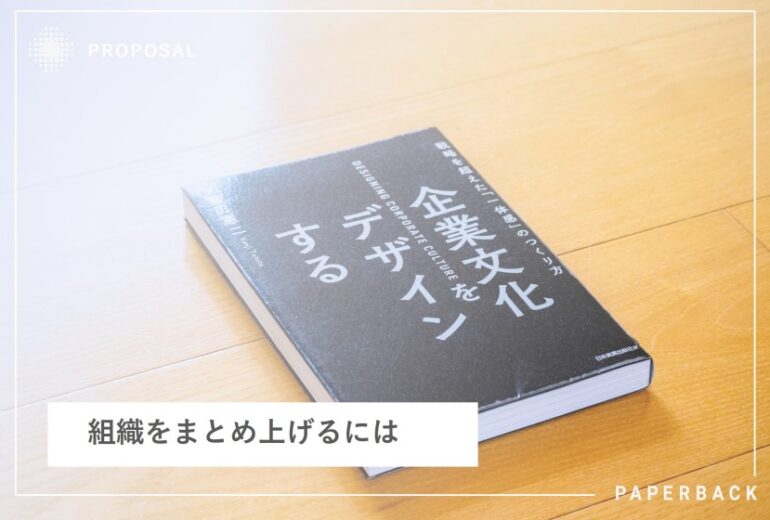
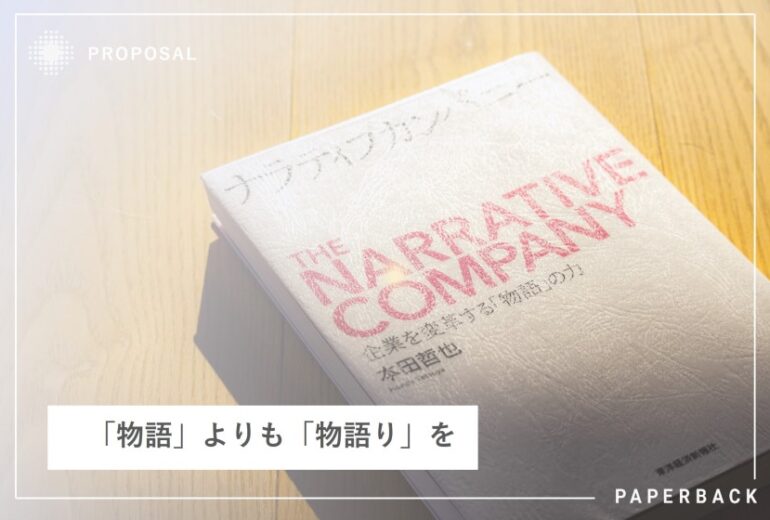

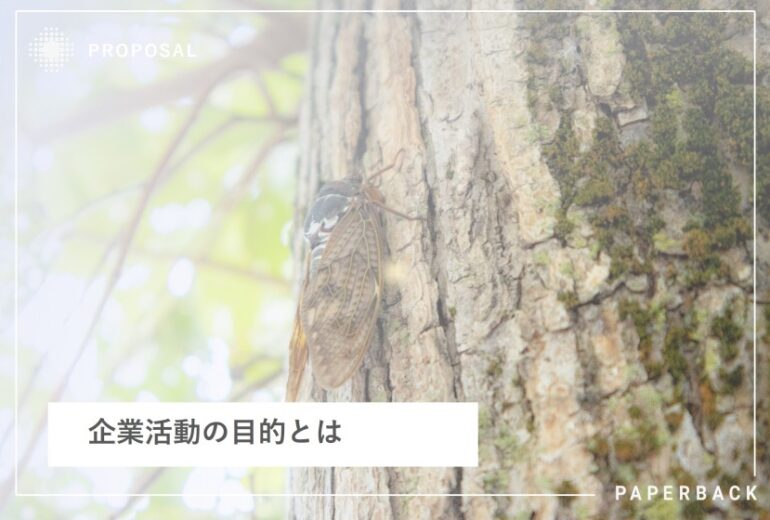
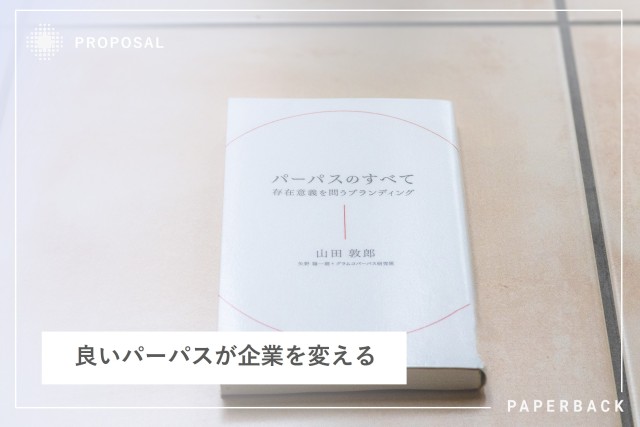


コメント