社員の1人ひとりは真面目で有能なのに、組織になると無能化する。
この、経営者ならば多少は感じるであろう現象を「構造的無能化」と名付け、そのメカニズムを解き明かした書籍が『企業変革のジレンマ』です。
組織の成功が、新たな問題を生み出す
事業が拡大していくと、スタッフが増えて組織化され、分業が進んでルーティンが確立されていきます。それは効率化をすすめた結果なのですが、反作用として仕事が「断片化」し、全体を統合する機能が「不全化」します。いざ改善しようとしても社内の抵抗にあい、やがては「●●部の意識が低いからだ」などと原因が安易にとらえられ、対応が「表層化」して抜本的な改善が放棄されます。その結果、企業は変化への対応力を失って、活力をなくしていきます。この状態を「構造的無能化」と言います。
著者は、「構造的無能化」は成功の代償であり、良い会社ほど陥りやすい「慢性疾患」だと言います。恐ろしいのは、大きな赤字を出すなどの逼迫した状況にはならないため、対応が遅れがちになることです。じわじわと組織が硬直化し、やんわりと推進力を失い、やがては衰退期に入っていきます。こうした「慢性疾患」にどう対処するかは、事業の継続性における死活的な課題といえるでしょう。
対話によって、己を知る
著者は、この慢性疾患を克服するキーワードとして「対話」をあげています。対話とは、「他者を通じて己を見て、応答すること」であり、「人が人とのコミュニケーションの中で思考すること」だと言います。この慢性疾患に対応するためには、マネジメントは部下を教育・説得するよりも、対話を通じて自社の現実を知り、考えを深めていくことが求められています。対話によって、断片化した組織を繋ぎ直し、一人ひとりが全体への視点を持てるようにすることが、構造的無能化への処方箋になるようです。
広報は、対話の一形態である
私たちは、広報活動もまた対話の一形態だと考えています。情報発信とは自分たちの想いを言語化し、人に伝えてリアクションを得ることです。日ごろの想いや取り組みをきちんと発信することは、社員や世間との対話のきっかけとなるでしょう。それはまた、他者を通して自分たちを知ることにもつながります。
本書の言う構造的無能化は「慢性疾患」ですから、改善するには生活習慣を変えるしかありません。地道な活動が大切なのは、広報においても同じです。短期的な見返りを期待するのではなく、コツコツと自分たちの考えを広めていく情報発信の仕方こそが、組織の課題を克服する一つの解決策にもなると考えています。
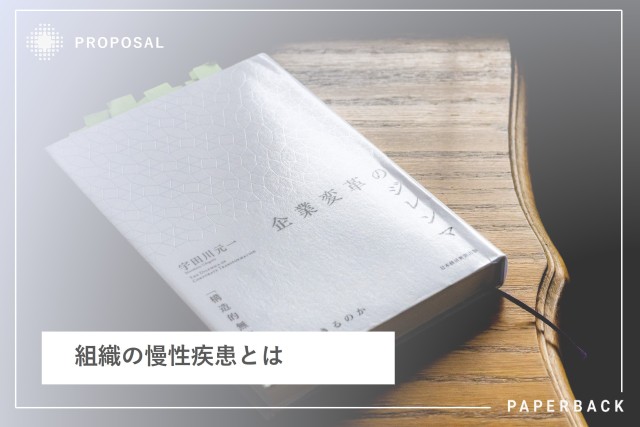
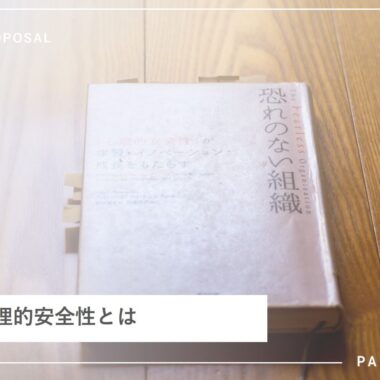
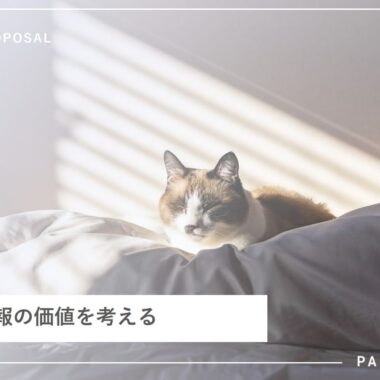
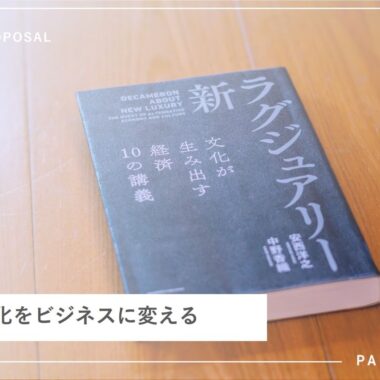

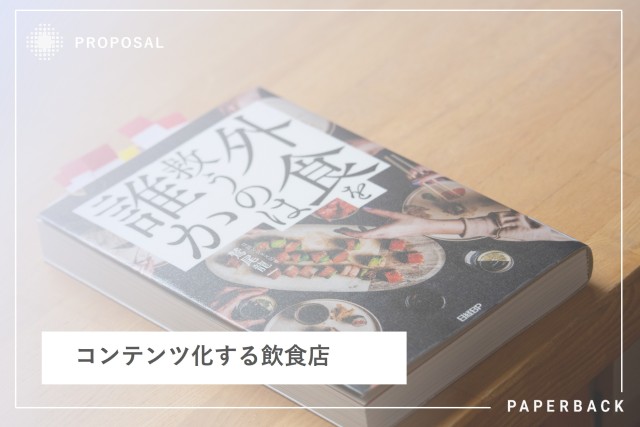
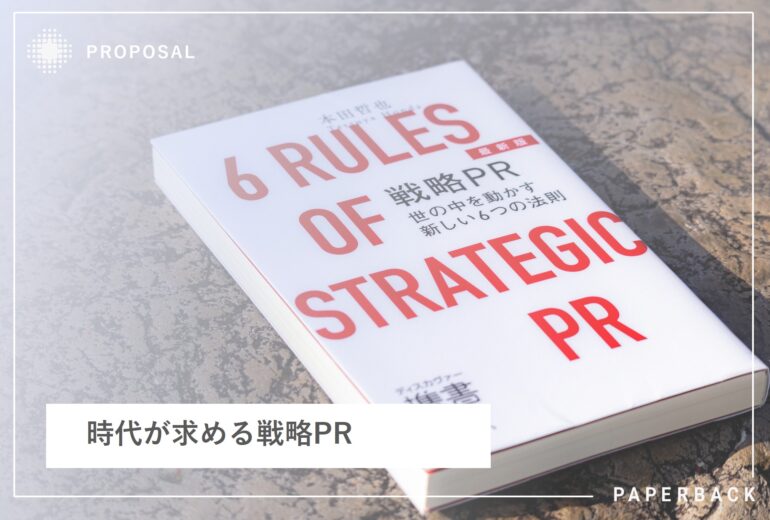
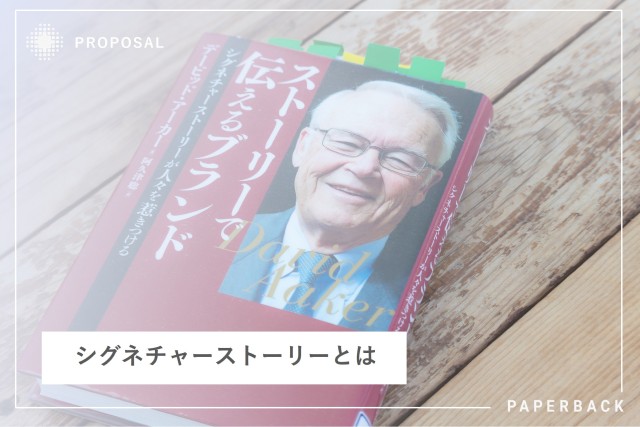
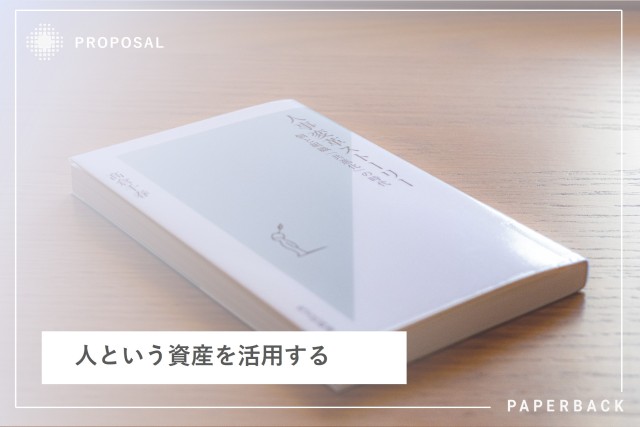
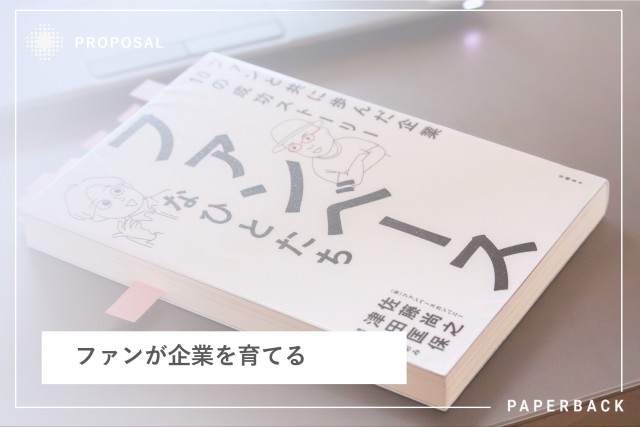
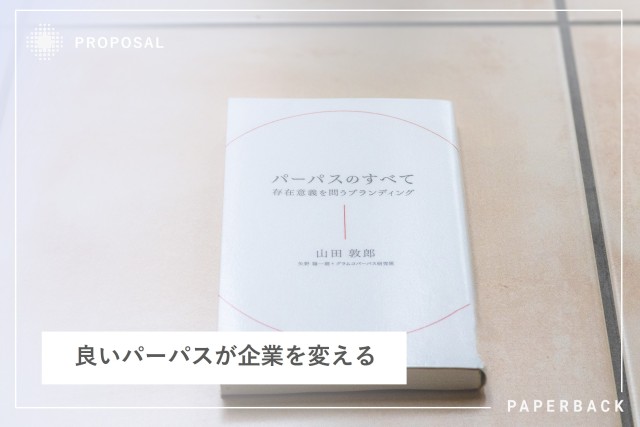


コメント