『外食を救うのは誰か』は、コロナ禍の2022年に出版された書籍です。この中では、パンデミックに関係なく、外食産業が直面する厳しい現状が語られています。
利益が出せない産業構造
近年、飲食業界でもDXが進み、グルメサイト経由のネット予約とキャッシュレス決済が一般化しました。仮に、グルメサイトの予約手数料が5%、カードの決済手数料が5%とすると、あわせて10%の利益が削られることになります。飲食店の経常利益率は良くて10%程度ですので、手数料だけで利益のほぼすべてを失うことになります。さらに食材や人件費、水光熱費の高騰を加味すると、利益を残すことが大変に難しいビジネスになりつつあります。
大手のシェアが増大している
その結果として、業界では全国チェーンの売上シェアが高まりました。本書によると、大手10社のシェアは13%にまで拡大しています。コストプッシュ型のインフレ下では、スケールメリットを生かし、価格競争力を発揮できる大手が有利です。
反対に、いま苦境に立たされているのは、シェアを奪われる個人店や中小企業でしょう。
飲食店はコンテンツ産業に
この『飲食店を救うのは誰か』は、その厳しい現状を踏まえ、解決策を探っていきます。大きな方向性としては、飲食店が広い意味でのコンテンツビジネスになっていくことを示唆しています。
本書は、飲食店の大きな強みを、食材や文化の魅力を物語として表現できることだとしています。成功事例として取り上げられた淡路島のカフェ「BALNIBARBI(バルニバービ)」は、人々から忘れ去られてしまったような何もない辺境の地にカフェを作り、新たな賑わいを創り出しています。周辺環境は、廃屋しかない荒れ地。地元の人ですら「何もない場所」と見向きもしないような土地でしたが、歩き回ってみれば、近隣には素晴らしい生産者がいて、蛙の声や波のせせらぎ、なにより夕日の美しさが格別だったそうです。ここで開いた最初のカフェが当たったことから、やがて店舗が増え、周辺にキャンプ場ができ、宿泊施設も生まれて、淡路島の新たな名所となりました。いまや専用のバス停まで設置されています。
「食事」という最強のコンテンツ
その土地にしかないロケーション・食材・文化・歴史を「食事」という誰もが好む人気コンテンツに変えられることが、飲食店の大きな強みです。これは画一化されたメニューでコストダウンを狙う大手とは真逆の戦略であり、地域密着の個人店が強みを発揮できる武器となるでしょう。
これまで多くの飲食店では、新規の集客をクーポン配布などの手段に頼ってきました。これが各種経費の高騰でもはや成り立たなくなってきています。これからは、その土地の価値、食材の魅力、ロケーションの素晴らしさをわかりやすいコンテンツに変えて人に伝えていくことが、飲食店の果たす役割になるのかもしれません。飲食店が文化の価値を再発見することは、地域の活性化にもつながります。それは飲食業の社会的価値の表現にもなっていきます。
飲食店が地方の課題解決に寄与しつつ、自らもビジネス上の成功を目指す、という時代が来たのかもしれません。私たちの事務所も、コンテンツ化の専門職として、業界に貢献していければと思っています。
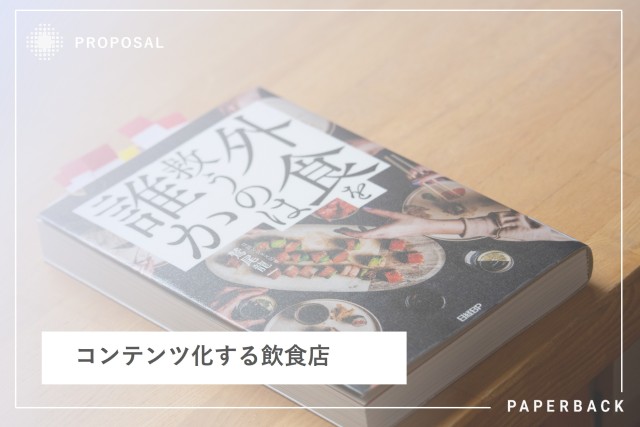
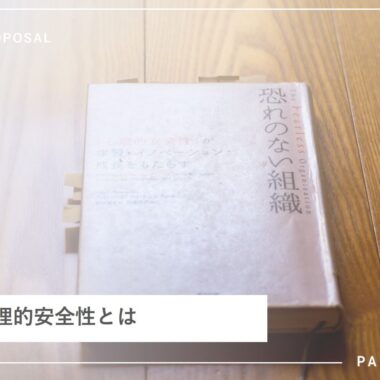
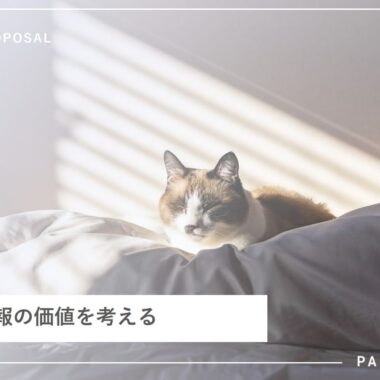
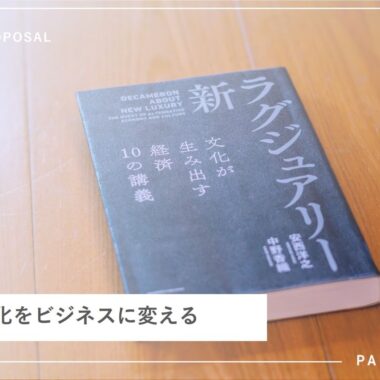

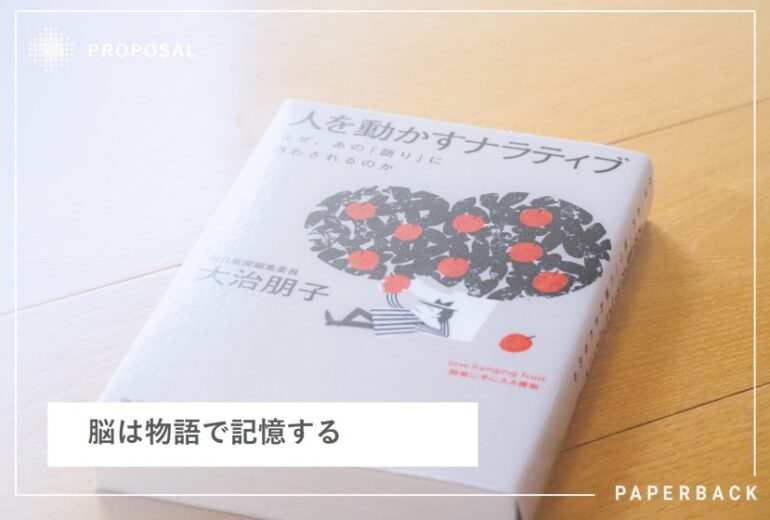

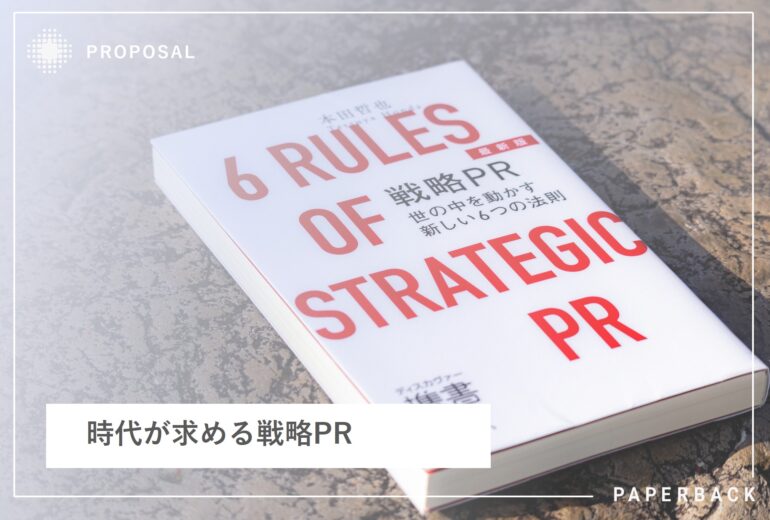
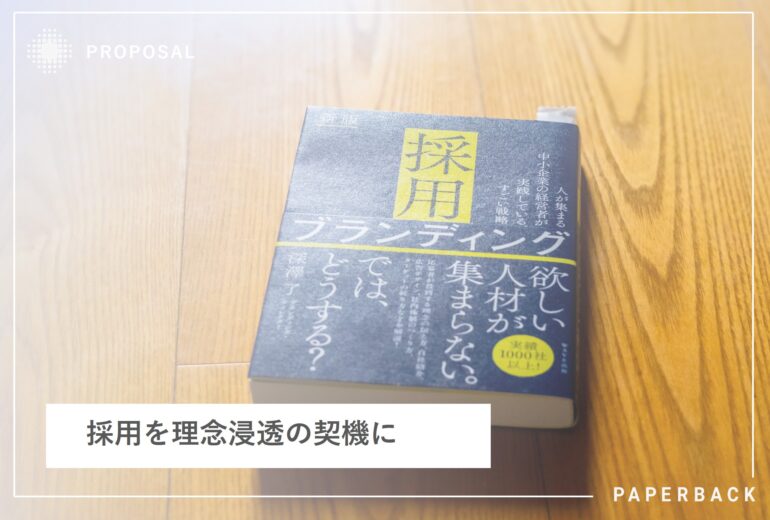
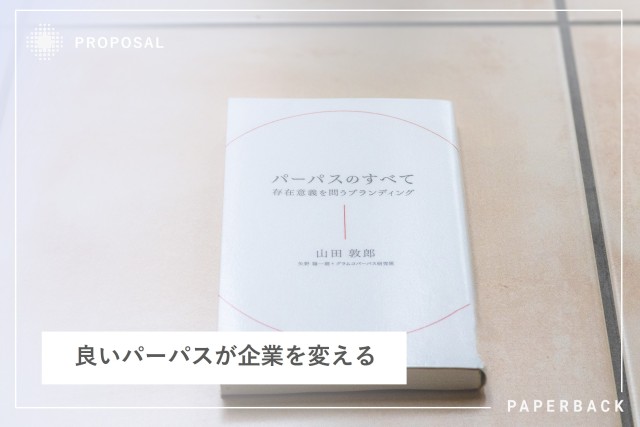
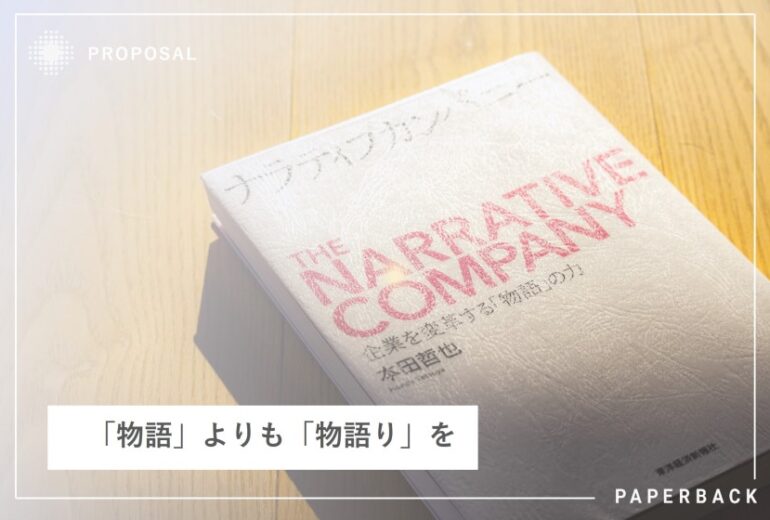


コメント