企業と顧客の関係性の変化を感じさせる書籍です。
かつて企業は、マーケットのニーズを捉え、的確にソリューションを提供することで成果を上げてきました。少し前までは、社会にまだ画一性があり、多くの人に共通する「困りごと」がありました。だからその解決策としての商品が成り立ち、これを大量生産することで、シェアを拡大して成長することができたのです。
従来のマーケティングが通用しない
こうした従来のマーケティング手法が通用しなくなっています。
生活レベルが向上し、不足しているものは無くなりました。商品のクオリティも一様に高まり、本質的な差別化はもはや困難です。一つのニーズに対して、圧倒的な投資でシェアを獲るという、大企業型のマーケティングはもはや過去の遺物となりつつあります。
ファンベースの考え方とは
こうした状況に対する答えとして「ファン化」を唱えるのが、クリエイティブディレクターの佐藤尚之氏です。彼は「ファンベース」という考え方のもと、顧客を収入源として捉えず、企業活動を支えてくれる仲間として位置づけ直すことで、顧客との新たな関係性を構築していけると説いています。
この考え方は、現代のメディア環境を考えても、必然的なものだと言えます。大量消費社会は、マスメディアによって支えられてきました。テレビなどの「大衆向け」のCMは、人々の欲望を画一化し、同じ商品を大量に売ることを可能としました。これが、いま大きく変わっています。SNSが主流となったことで、大衆向けのマーケティングは成果を上げられなくなり、むしろ1人ひとりの顧客としっかり対話をすることが求められるようになっています。
顧客と同じ物語を共有する
この著作『ファンベースな人たち』では、企業とファンが、商品の機能性ではなく、情緒価値で結びつく姿をイメージしています。その際に、重要となるのが企業の掲げるパーパスです。企業の社会的存在価値を訴え、これを顧客と共に実現していくことで、多くの人をその活動に巻き込んでいけます。
顧客を大切にする意味とは
例えば、スープストックは、「世の中の体温を上げる」をパーパスに掲げています。社員の一人ひとりは、どうやったら「世の中の体温があがるのか」を考えて、店づくりをします。お客様を迎える際には、「自分の大切な人のお兄さんやお姉さんが来ると思ってお客さまと接する」ことが基本となっています。お店を清潔に保ち、心地よく過ごせる空間を作って、いくつものスープを温めておくのは、お客様を大切な存在だと考えるからです。
物を売ることではなく、スープを媒体にした関係性を築くこと。そこに焦点を当てるからこそ、ファンが増えていくのでしょう。
パーパスを掲げて社内に浸透させ、理念と行動を一致させて、それを物語化してWEBやSNSで広く伝えていく。それが、これからの時代のマーケティングの基本になると考えています。
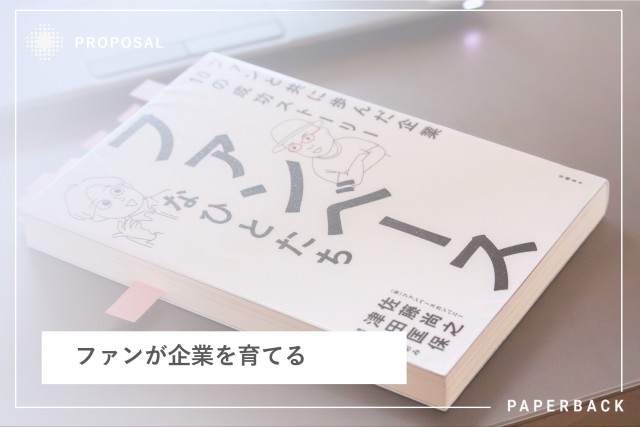
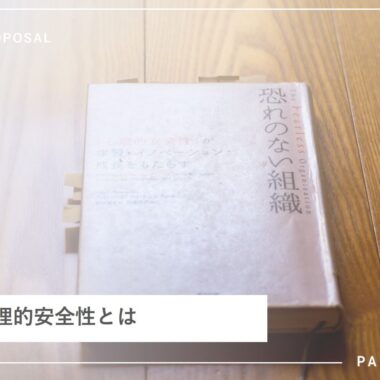
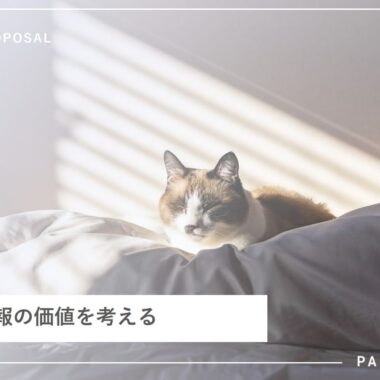
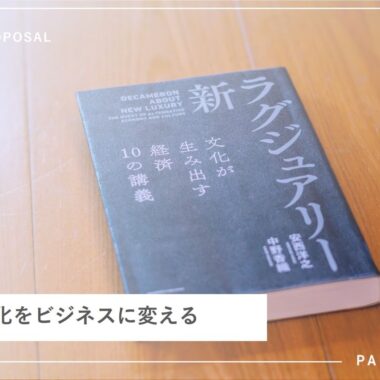

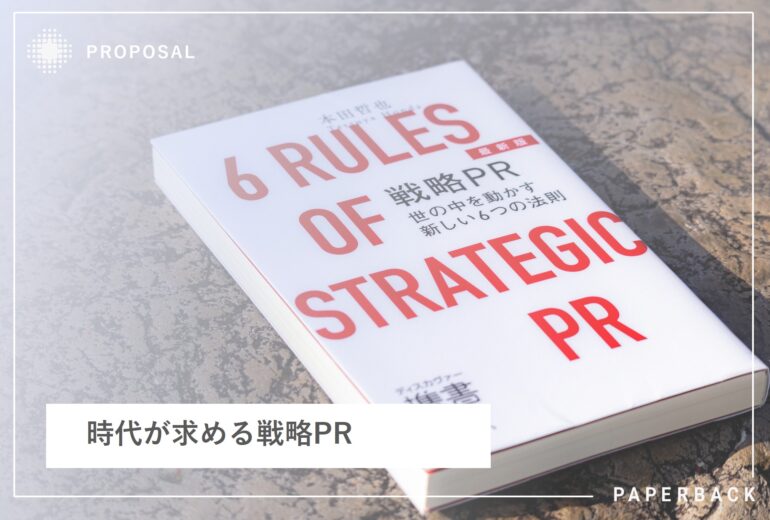
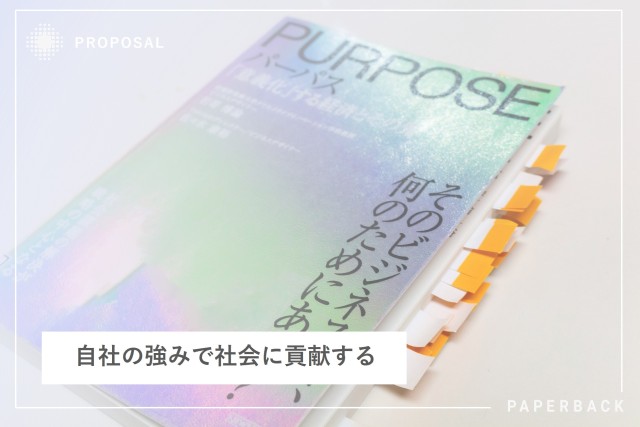
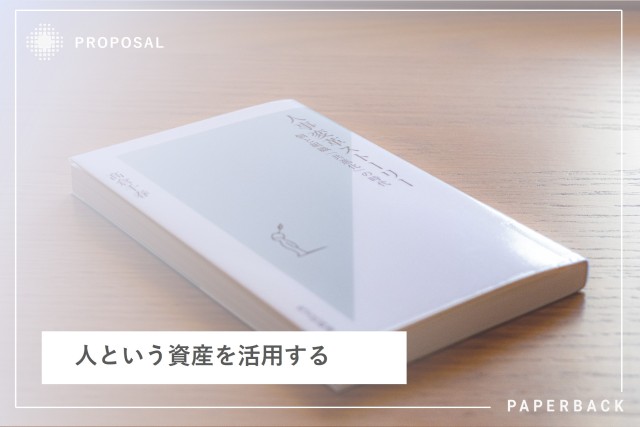
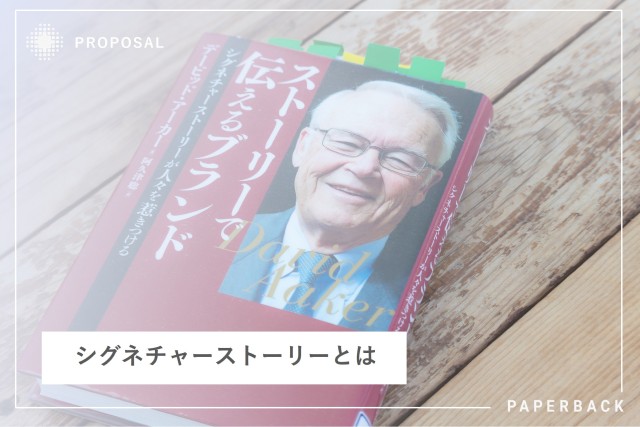
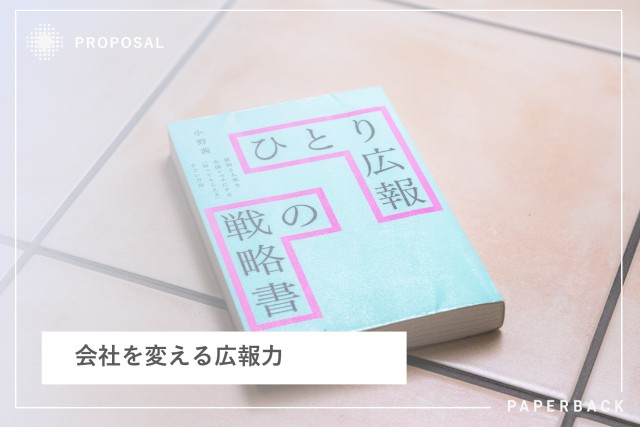
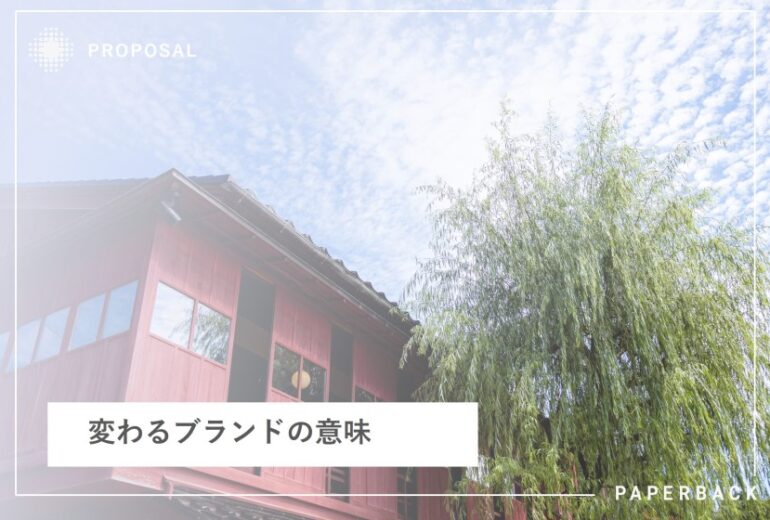


コメント