『ストーリーが世界を滅ぼす』とは、やや衝撃的なタイトルですが、逆説的に物語の力を実感できる書籍です。
物語は人々をまとめる唯一の手段
同書は、物語とは人々をまとめる唯一の手段である、と言っています。人々はずいぶんと昔から、物語を活用してきました。原始的な社会を研究すると、優れたストーリーテラーがいた部族は、生き残る可能性が格段に高かったそうです。共同体をまとめる物語の多くは、組織への忠誠を善とし、仲間と離れて生きていくことの危険を強調します。組織の価値観に従わない人間を悪とみなし、これを断罪することで組織を結束させていきます。それらは反作用として、他部族への不寛容を生み出します。
物語の危険性とは
人々を団結させるには、聞く人を魅了し、意識に影響を及ぼす優れた物語が必要です。こうした物語の多くは、大変に分かりやすく作られます。現実の複雑さを無視して世界を単純化し、正義と悪の2つに色分けすることで、人々を熱狂させるのです。ナチスは国民の不遇はユダヤ人に責任があるとしました。ルワンダのフツ族は、ツチ族を悪魔として語りました。これらはみな同じ原理です。歴史のなかで正義という概念は人々の怒りを正当化するために使われてきた、と本書は言います。
科学と啓蒙主義
こうした危険性への対抗策として生まれたのが、科学と啓蒙主義です。宗教的信念に基づいた絶対的な正義は、妥協のない対立を生み、時には大規模な殺戮すら引き起こしてきました。これを乗り越えるためには科学に基づいた客観的な真実が有効だったのです。
SNSの発展で変わる世界
この試みは、ある程度の成功を収めたと言えます。差別や偏見は、かつてに比べれば確実に少なくなっているでしょう。一方で、SNSの発展が再び原始的な社会への逆行をもたらしています。かつて部族をまとめた語り部は、いまは刺激的な物語を発信するインフルエンサーに置き換わりました。情報化社会では、語られる「真実」に対して、いくらでも都合の良いエビデンスを見つけることができるため、虚実の境目は曖昧なものとなっていきます。科学もまた力を失いつつあります。
SNSを調査すると、面白く作られた偽情報は、つまらない真実の6倍速く広まるそうです。また感情が込められた投稿はリポストされる率が高く、なかでも「怒り」の感情は伝播するのが早いことが観測されています。
これらの事実は、逆説的にですが、物語の持つ強い力を証明しています。企業広報では、物語のポジティブな面に目を向けながら、客観的な事実を大切に、健全な情報発信を進めていく必要があるのでしょう。
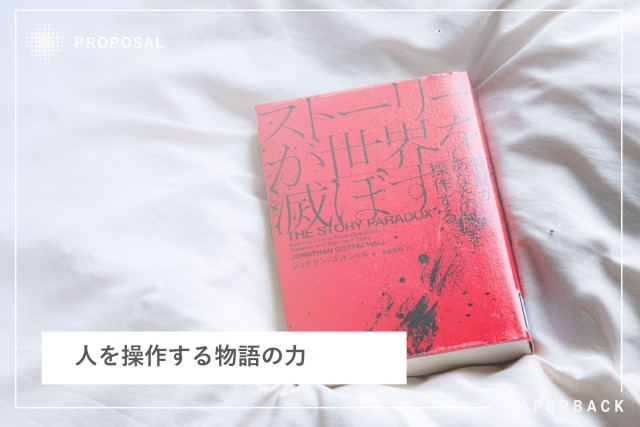
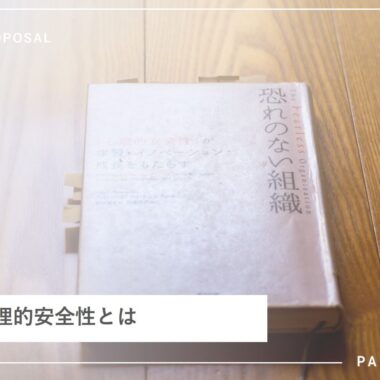
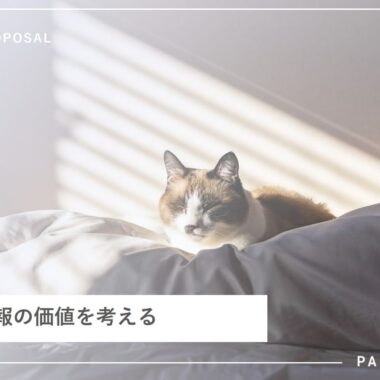
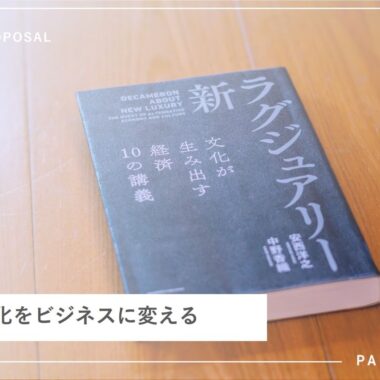

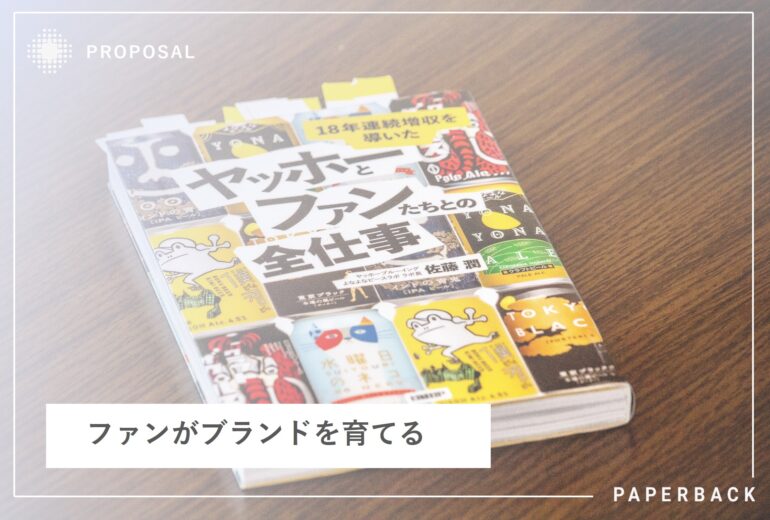
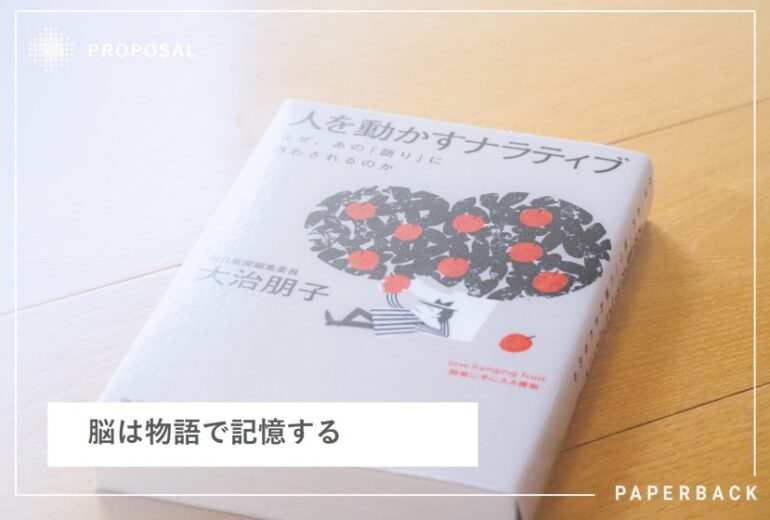
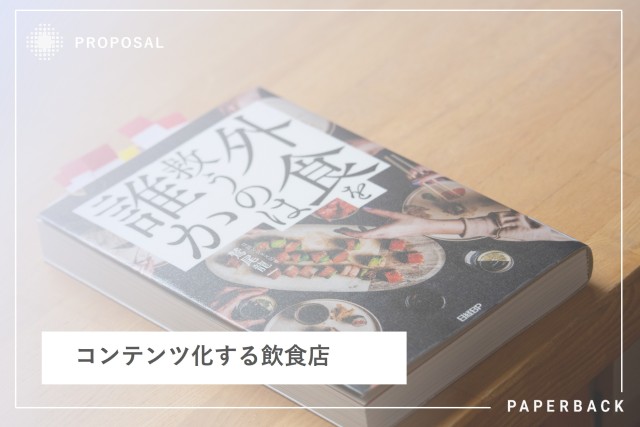
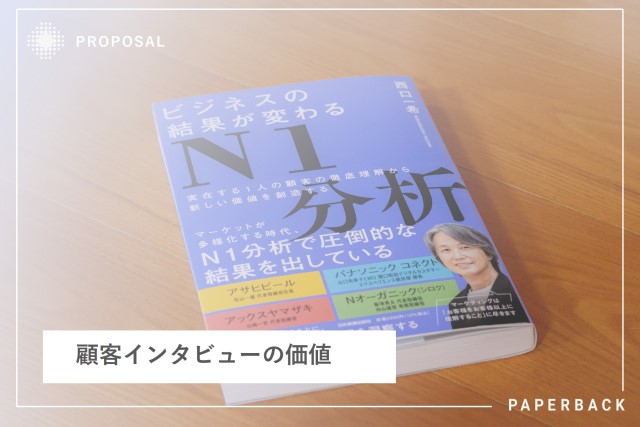
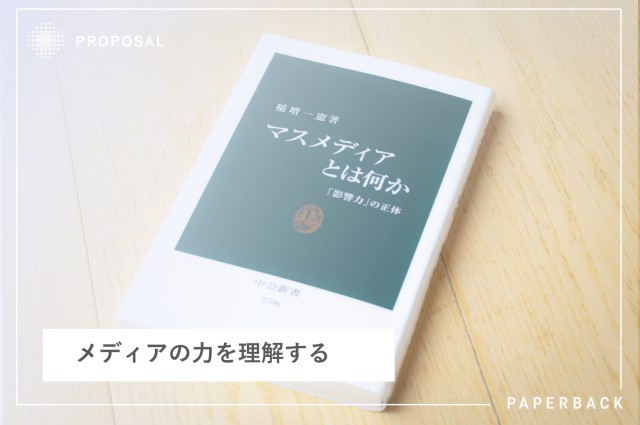
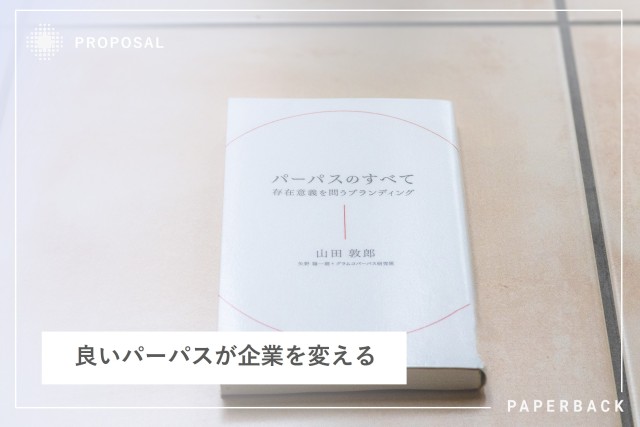


コメント