最近、大手メディアへの批判をよく耳にしますが、このメディア研究者の書いた『マスメディアとは何か』によると、その影響力は過大評価されているといいます。調査をしてみれば、そもそもメディアには、世の中を動かすような力はないそうです。第二次世界大戦時のナチスによるプロパガンダですら、実はさほど人々の思考に影響を与えていませんでした。これは、戦後処理のなかで、「ドイツ国民はナチスに騙された」というストーリーを補完するために誇張されて伝えられた、神話の一つだと言います。
メディアの持つのはアジェンダ設定力
しかしながら、私たちは、しばしばメディアが強い影響力を発揮する姿を目撃します。それはマスメディアがいまも、「アジェンダ設定」において強い力をもっているためです。
例えば、2024年の一時期、兵庫県の斎藤知事が大きな話題になりました。テレビの批判的な論調に反して彼が知事に再選されたことから、メディアの力の衰えが指摘されましたが、そもそもテレビや新聞が取り上げなければ、これほど多くの人が兵庫県知事について話題にすることなどなかったでしょう。
人は意外と健全である
議論すべき事柄をテレビや新聞が決め、SNSで活発な議論が行われる。その結果人々の行動が変わるのであれば、民主主義としてはむしろ健全な方に向かっているように思います。
一方SNSの危険性も指摘がされています。その一つが、似た考えばかりに触れることで思想が硬直化していく「エコーチェンバー」です。もちろん、こうした負の側面あるとしても、影響力を得るためには、ある程度大衆向けに発信しなければならないので、極端な思想はさほど多くないと言います。また、Xなどは自由にコメントを付けられることから、肯定・批判双方の意見が並ぶケースも多く、意識しなくとも、違う考えに触れられるようになっています。
総じて、人々が心配するよりもメディアもSNSは問題は少ないし、そもそもそんな力もない、というのが本当のところかもしれません。
説得ではなく、共感を
こうした研究が明らかにしたのは、メディアを通じて人を説得することは難しいという現実です。人間は、自分の考え方を変えることに強い抵抗を示す習性があります。私たちが広報戦略のなかで目指すべきは、説得でなく共感なのです。反対意見と戦うことはやめて、企業の掲げる夢を宣言し、価値観の近い仲間を集め、共感を広げていくことが現代の広報戦略が目指すものとなるのでしょう。
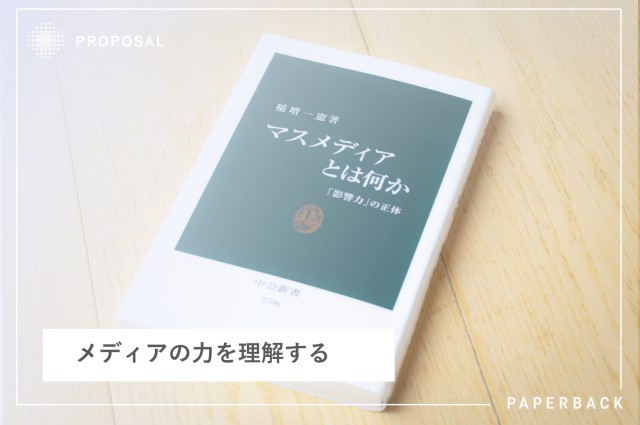
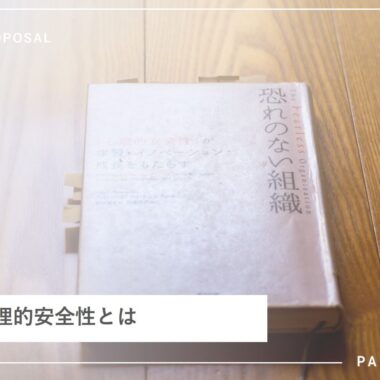
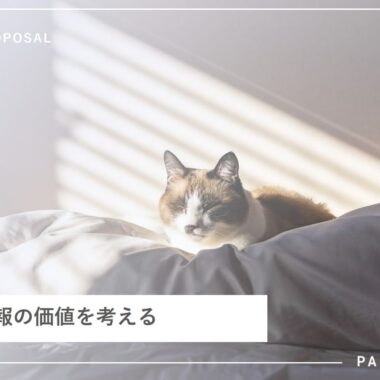
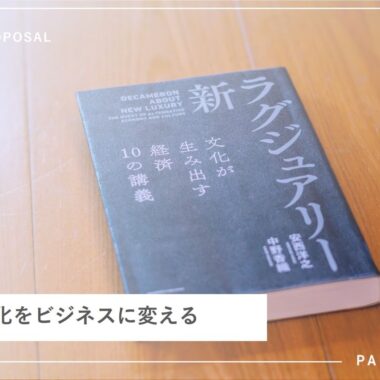

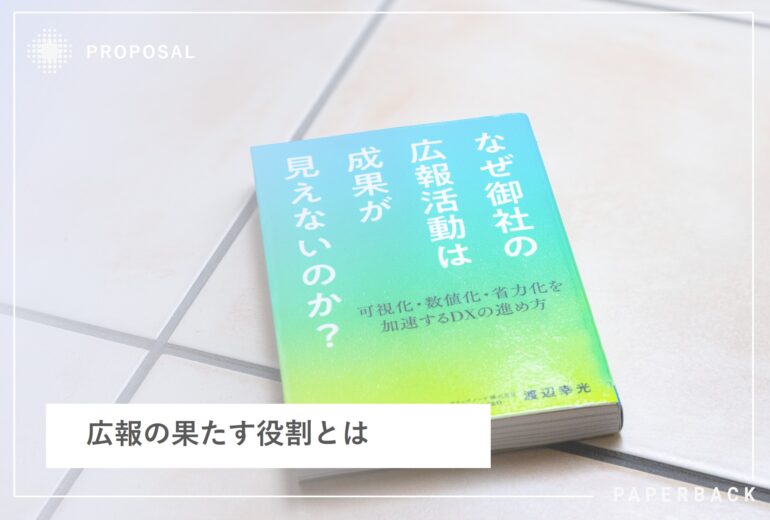
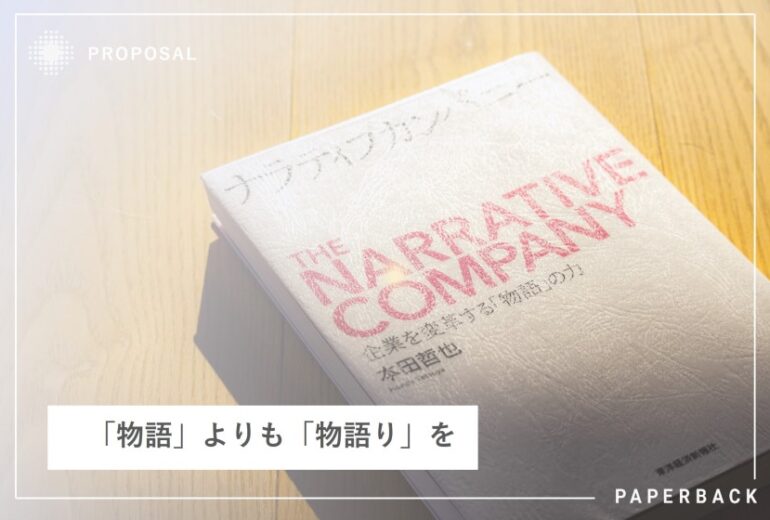

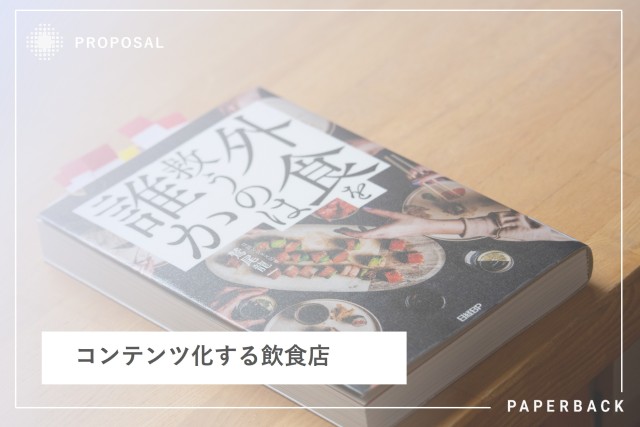




コメント