人類が生きてきたほとんどの時代で、情報には高い価値がありました。
情報を多く持つことは、競争に勝つこと、生存確率を上げることに直結しており、人々はそこに高い価値を感じていました。80年代くらいまでは、情報に飢えていたともいえるでしょう。往時のマスメディアは、こうした欲望に応える形で、強い影響力を発揮してきました。
情報過多の時代の広報とは
しかしいま、状況は大きく変わっています。情報は飽和し、人の処理能力をはるかに超えたデータ量が行き交うようになりました。もはや、情報そのものに価値はないともいえます。本書『なぜ御社の広報は成果が見えないのか』は、こうした世の中では、広報の考え方も変わっていくべきだと説いています。
これまでの広報の効果測定は、広告の影響を強く受けてきました。なかでも特徴的なのはリーチ(量)の重視です。テレビ番組であれば視聴率やその合算であるGRP、新聞や雑誌なら発行部数によって価値を測る考え方が採用されてきました。WEBマーケティングでもインプレッションが重要な指標のひとつとされますが、これらはすべて、単純な露出量を測るものでしかありません。
広報の業界でも、プレスリリース配信サイトなどに登録すれば、数十ものメディアにリリースが掲載され、広告費換算で数十万とか数百万円という成果がでます。しかし、このあり方にも違和感があるといいます。
「忘れる」という能力を持った人々に
かつての情報不足の時代には「覚える」ことが、重要な能力でした。しかし情報過多の時代になると、むしろ「忘れる」能力が求められます。昔は、一人がCM3回見れば覚えるといった経験則がありましたが、今では10回見ても忘れるものは忘れるでしょう。つまり表示されたからと言って見られたとは限りませんし、見られたからと言って覚えられたとも限りません。そうしたなか、企業の情報発信にどれだけ価値があったかを測るには、新たな考え方が求められています。
広報の5つの段階とは
本書『なぜ御社の広報活動は成果が見えないのか』では、広報には5つの段階があり、より高い段階を目指すべきだと説いています。
1の段階は量の欲求、とにかくメディアに取り上げられたい。露出を増やしたい。
2の段階は質の欲求、メディアやフォロワーとの信頼関係を深めたい。
3の段階は効率化の欲求、システムをつくり自動化したい。
4の段階は承認の欲求、ステークホルダー「部署内の同僚」「社内の同僚」「経営陣」「メディア」「投資家」「消費者」「同業者」「市井の人々」に認められたい。
5の段階は経営と社会貢献の欲求。自社の存在価値を社会と共有して広めていきたい。
つまり、露出の量を追求し目先の利益を目指す広報から、本当の意味での企業価値を高める活動へと段階を上げていくべきだという主張です。
広報は、やがて経営の課題となる
露出の量によって効果が決まる時代では、圧倒的に大企業が有利でした。資金量がモノを言うので、中小企業には戦う術はありません。そのため、ほとんどの中小企業では戦略的に情報発信を考える部署が存在せず、広告出稿するとしてもお付き合いレベルのものばかりでした。上の5段階に即していえば、最初の段階にとどまっていた、と言えます。
しかし、段階が進んでいる企業では、情報発信は企業の存在価値に関わる重要な課題と位置付けられており、経営者が直接関与して戦略的に進めています。特にWEBやSNSは、マス媒体よりはるかに安価に取り組めることから、相対的には中小企業に有利な状況になっているともいえます。
戦略的に広報を考えられる人材を
これから、広報担当者は貴重な存在となっていくでしょう。コンテンツ制作に関する一定のスキルを身に着け、ニュースリリースの配布やメディア対応のみならず、自社の価値をどう高めていくかを戦略立てて考え、実行できる人材を確保することは、事業の成長においても必須のものとなります。
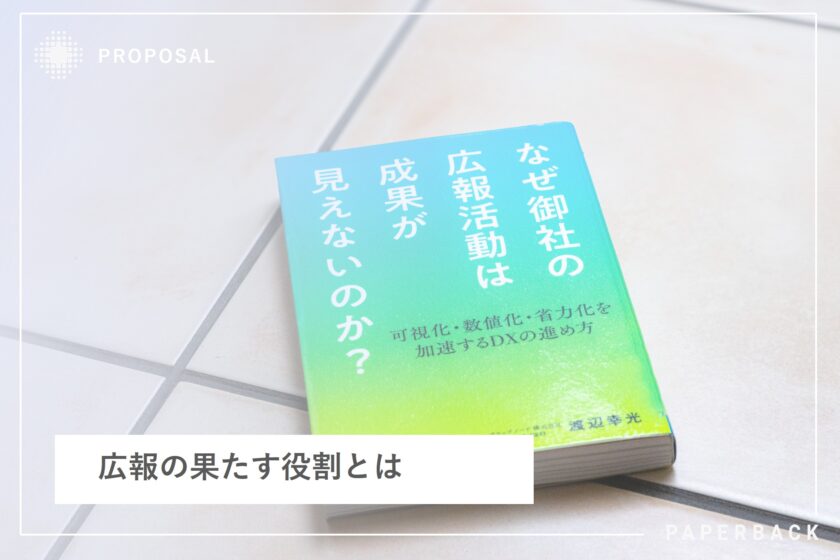
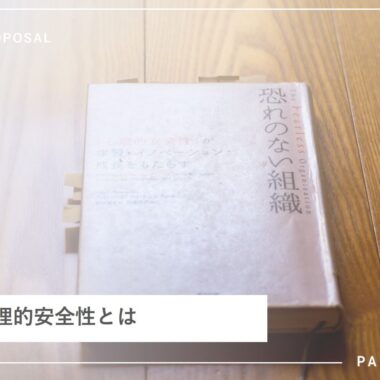
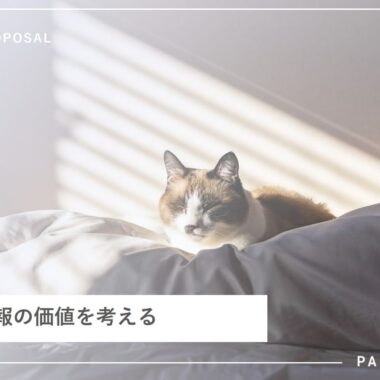
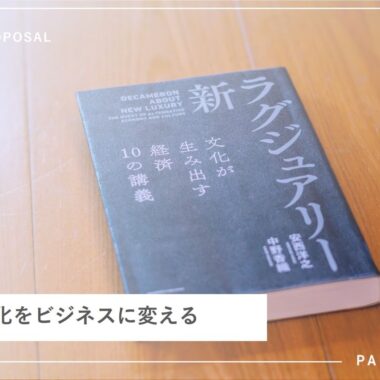

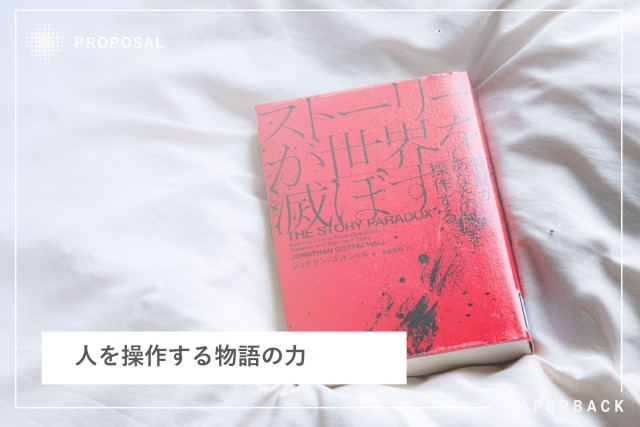

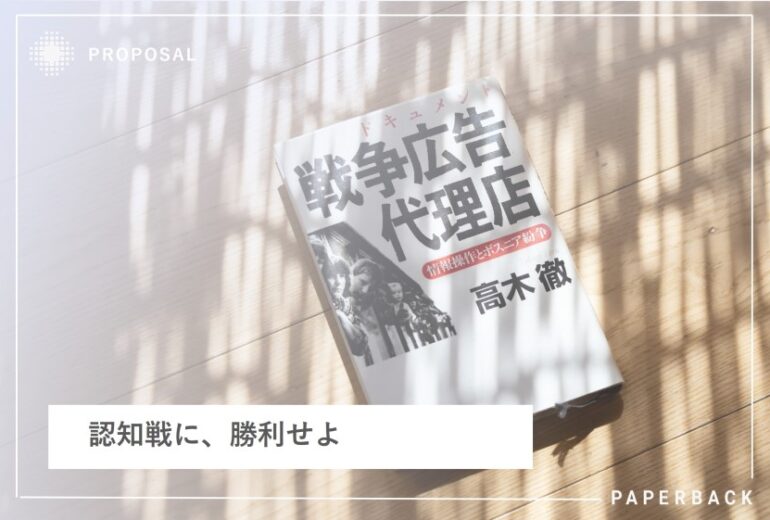
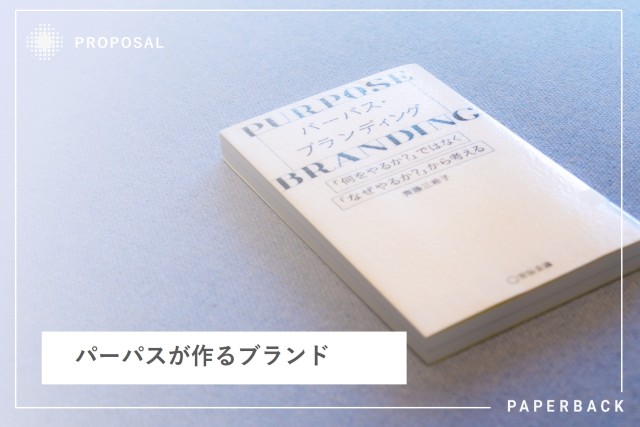
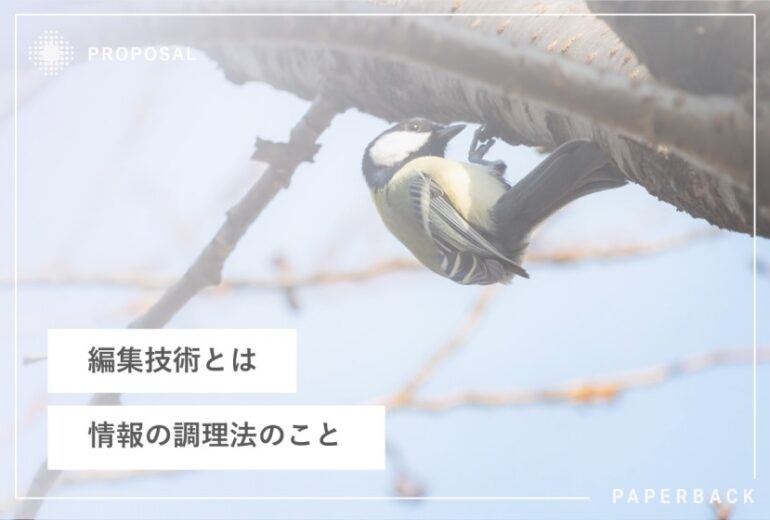
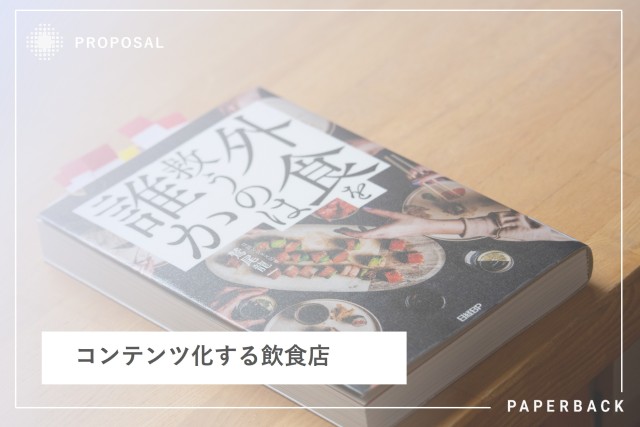


コメント