SNS全盛の時代になり、企業と顧客の関係も変わりました。いくつかの企業では、顧客を利益を与えてくれる存在ととらえることをやめ、ともにビジョンを追いかける仲間と位置付けています。ヤッホーブルーイングは、まさにその先頭を行く企業です。
ファンとともに育つブランド
本書を読むと、ヤッホーとそのファンのすごさがわかります。
あるヤッホーのファンは、自主的にヤッホーを広めるイベントを企画して運営し、別のファンは、本業がシンガーソングライターだったことから、無償でヤッホーの歌を作りました。彼らにとって、ヤッホーブルーイングの作るビールは、単なる商品を超えた何か別の価値を持つものになっているのでしょう。
なぜ、そんなファンが増えていったのか。一つには、明確なビジョンを掲げたことが要因です。世界にはビールは150種類あるそうですが、日本では大手メーカーの寡占状態ということもあり、「ラガー」と呼ばれる1種類がほとんどのシェアを占めています。ビール文化の多彩さや奥深さを広めたい、それが同社のビジョンです。「水曜日のネコ」「インドの青鬼」といった、およそビールとは思えない個性的なネーミングも、決してふざけているわけではありません。企業のパーパスに根ざした戦略であり、共感を集める施策なのです。
コアなファンが市場を広げる
業界の構造も大きな影響があるようです。クラフトビールのシェアは、およそビール全体の1%といいます。つまり100人に1人くらいの割合ですから、普通に生活していてもクラフトビールファンに会える機会は多くありません。ですから、彼らはヤッホーを介して仲間に出会うことができると、すぐに意気投合するそうです。よなよなエールが好きな人は、その時点で仲間なのだと言います。
資料を見ると、ヤッホーブルーイングの年商はおよそ200億円あります。いくらコアファンだといっても、一人の人間が飲むビールの量などたかがしれています。年間の消費金額は数万円程度でしょう。ヤッホーを支えているのは、コアなファンというよりも、もっと幅広い人たちでしょう。中心的な存在である熱狂的なファンを大切にすることで、より世間に広げていくことができるという良いお手本なのだと思います。
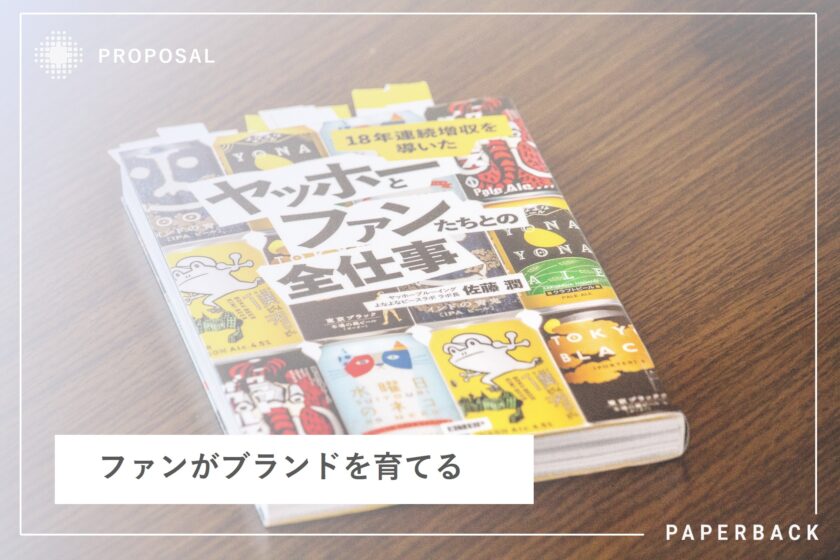
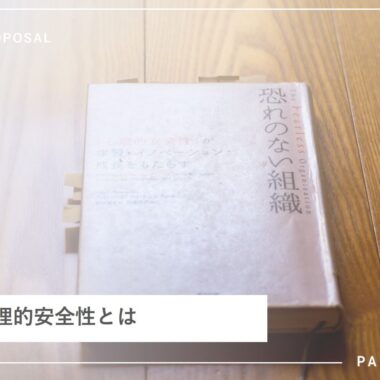
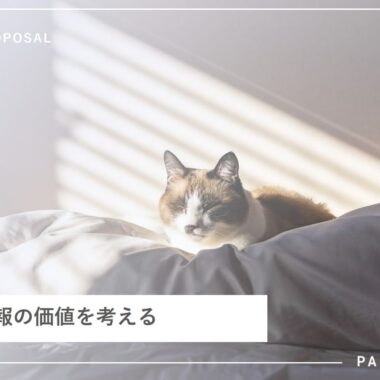
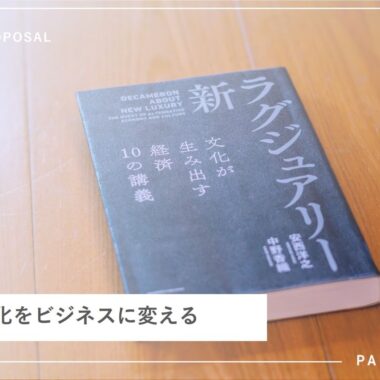

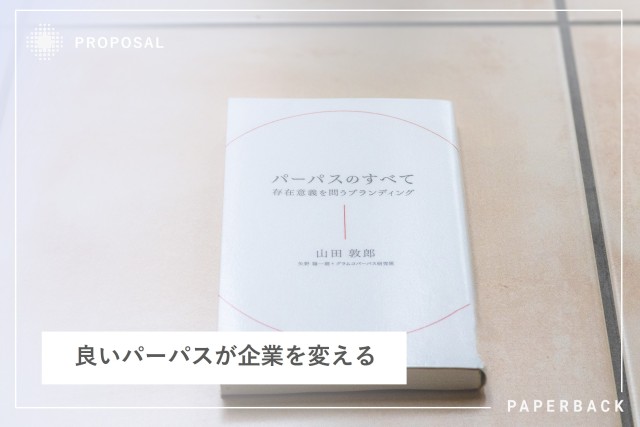
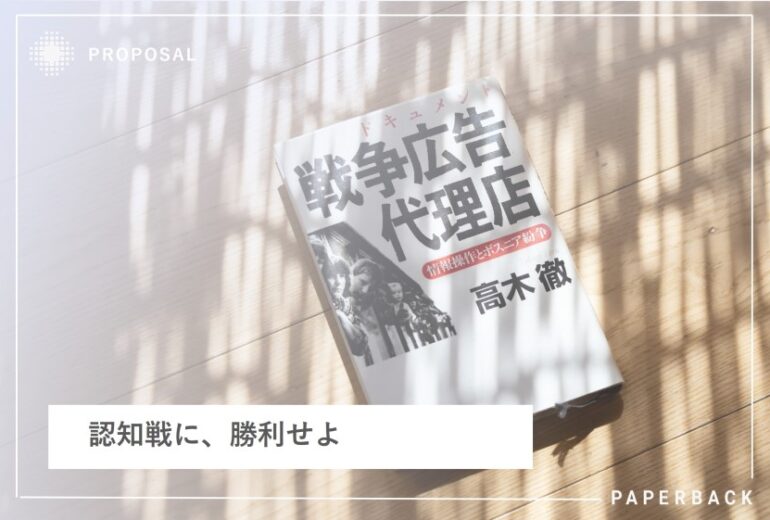
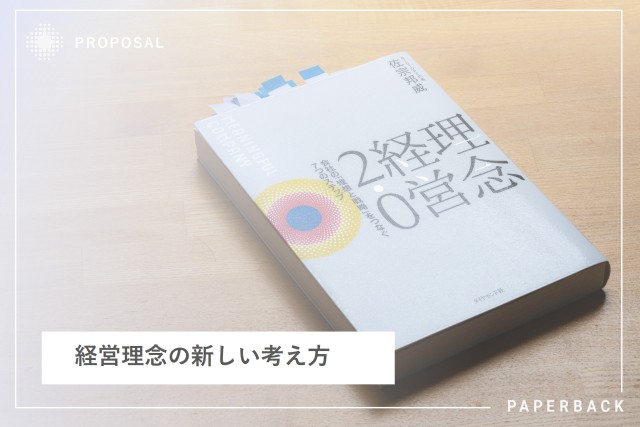
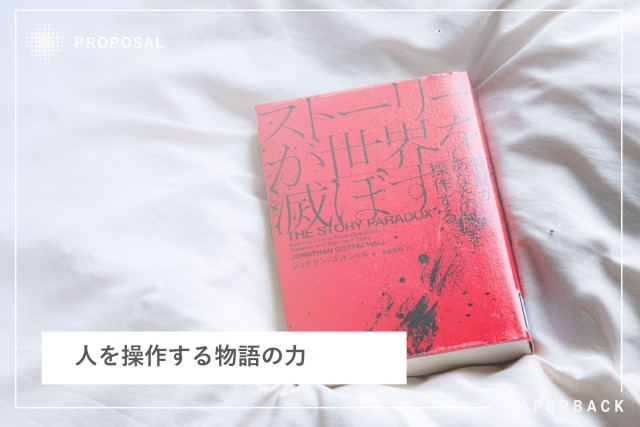
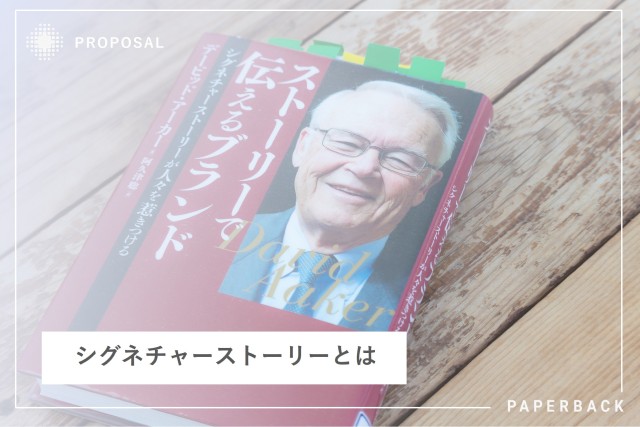
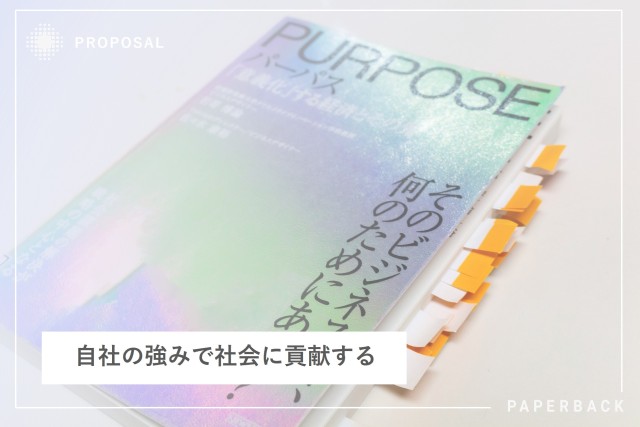


コメント