『宗教を生み出す本能』は、生物学者が書いた宗教の本というやや変わった内容です。
利他的な行動は、生物の本能
世のため人のためにというとどこか人間的で、自分のことしか考えない人は野蛮なイメージで見られます。しかし、実際はそうではないといいます。例えばミツバチは女王を守るために自ら命を捨てますが、このような自己犠牲は多くの生物にみられるものです。
生物は、生き残るために群れを作ります。
群れの内部では利己的な個体が優位に立ちますが、外部に対しては利他的なグループのほうが優れています。人間は、荒野のなかで孤立して生きていくには弱すぎ、群れを離れることはすなわち死を意味しました。集団を維持することが生き残りのカギとなる世界では、利己的でルールを守れない個体は淘汰されていきます。つまり私たちは、本能レベルでは、むしろ利他的な行動を身に着けているといえるのです。
自我があるなかで、自己利益を犠牲にできるか
しかし、問題は簡単ではありません。ミツバチのような単純な生き物であればDNAに命じられるままに命を捨てることができるでしょう。一方で、人間には自我があります。自らを犠牲にしてまで他人に尽くすことに、抵抗を感じるだけの知能を得てしまっています。そうしたなか、共同体を一つにまとめるために必要だったのが、超自然的な存在や英雄的な自己犠牲の物語です。やがてそれは、宗教という形になっていきます。
現代の風潮のなかでは、自己犠牲というのは流行らないかもしれませんが、ほとんどの強い組織というのは、利他的に振る舞う文化が根付いています。時折、一体感の強い会社のことを「宗教のよう」と揶揄することもありますが、利他とはある種の自我を超えた心境なのですから、周囲からみれば異常に見えるのは当然です。
理念やパーパスへの共感が、強い組織を作る
40代~50代くらいの世代までは、終身雇用が前提でした。会社とは、自分の生存を保証してくれる貴重な共同体ですから、利他的にふるまう動機が強くあったでしょう。現在では、会社への帰属意識は薄まり転職や独立のハードルが下がっています。組織に属さなくても、WEBやSNSを通じて社会参加することも可能となりました。自己利益を犠牲にしてまで、集団でいることの意味は希薄になっています。こうした社会において、組織に利他的な行動を根付かせることは簡単ではありません。ですから大きな使命、ビジョンやパーパスといったものへの強い共感が、より大切になってきているのでしょう。
なお、これは個人的な感想ですが、利他的な「お人よし」がきちんと出世できるかどうかは、その組織の健全性を図る物差しにもなるように思っています。
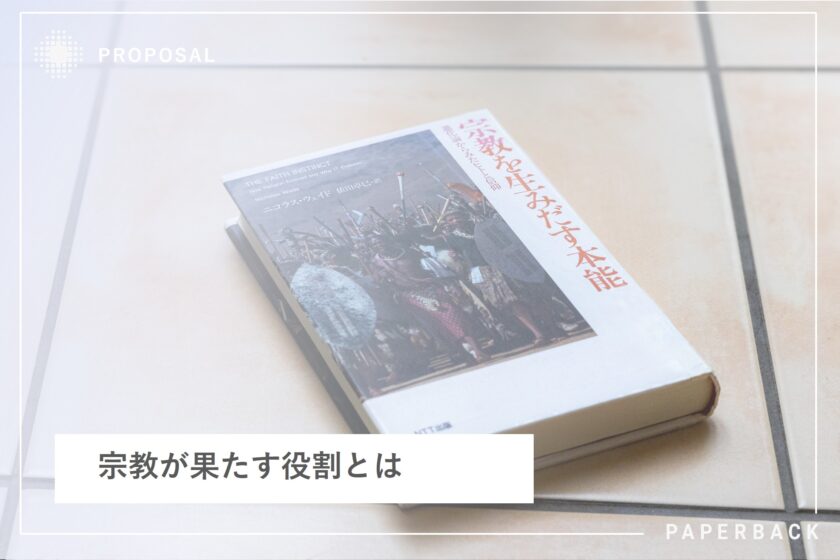
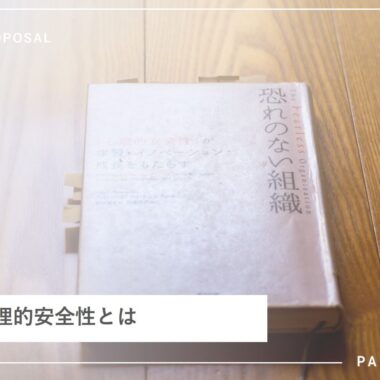
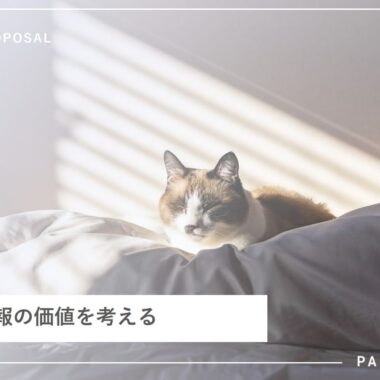
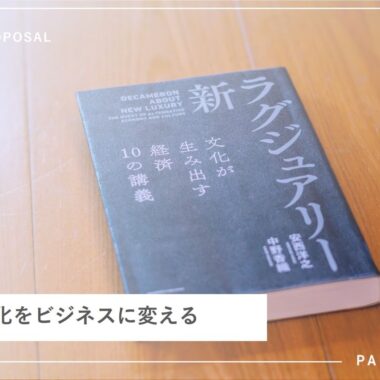


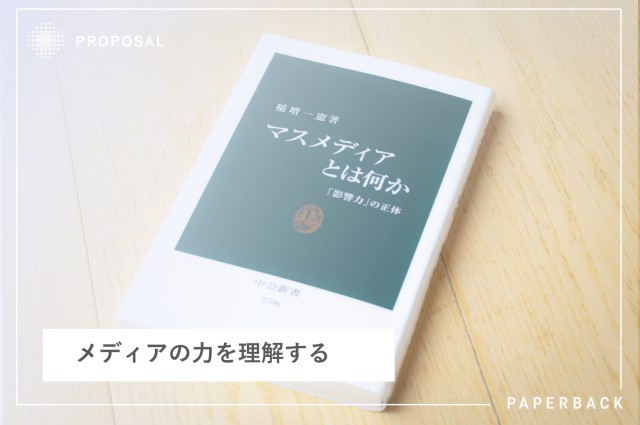
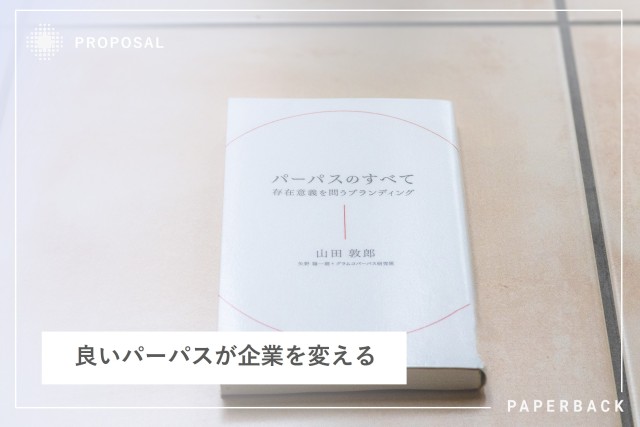
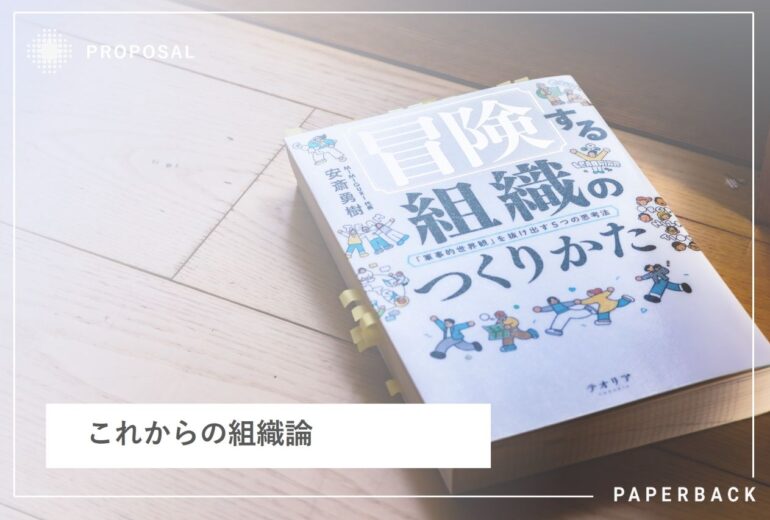
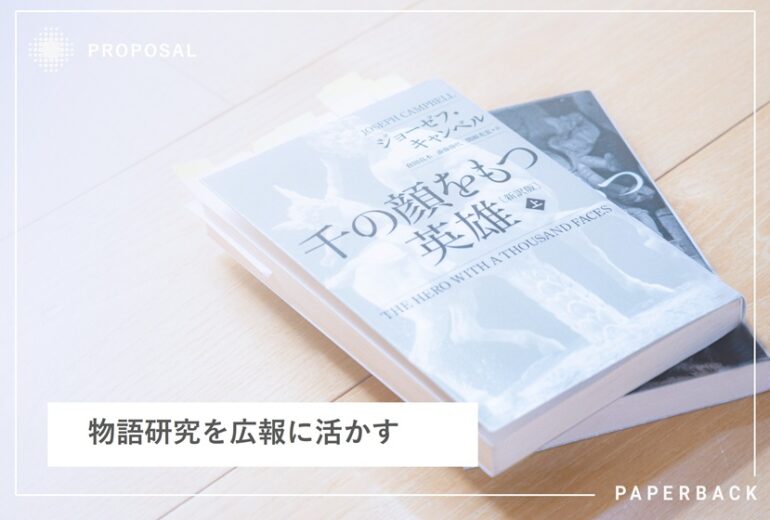
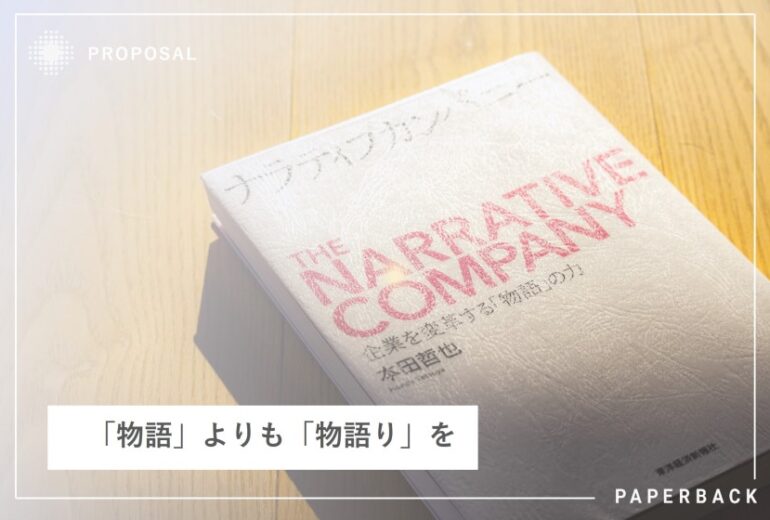


コメント